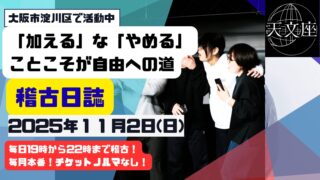稽古日2025年11月1日
先日の稽古で、演出家から投げかけられた言葉が、ベテラン俳優たちの心に深く刺さりました。
「現状維持は死だ。成長以外に道はない」
30年、40年とキャリアを重ねた俳優たちに向けられたこの厳しい哲学。なぜ経験豊富な俳優ほど、自分の演技を根底から見つめ直す必要があるのでしょうか。
経験という名の「無意識の罠」
長年芝居を続けていると、不思議なことが起こります。身体が勝手に動くのです。セリフを聞けば自然と表情が変わり、呼吸が生まれ、言葉が出てくる。
これは技術の証です。しかし同時に、大きな危険性も孕んでいます。
「長年お芝居やってると、わかんなくなってくる」
確かにクオリティは高い。でもそれは、「それっぽくできてしまう」だけかもしれません。この状態を続けると、新しいものが自分の中に生まれなくなってしまうのです。
車の運転に慣れると何も考えなくなるように、俳優も無意識で「それっぽい」動きをしてしまう。この罠から抜け出すカギは、**「無意識でやっていることを、どれだけ意識化して、また無意識に落としていくか」**という終わりなき繰り返しにあります。
俳優の仕事とは何か?—「自分から始まる」という原則
演出家は、俳優の仕事の定義を改めて問いかけました。
「俳優の仕事とは、自分から始まって他人の皮を被ること」
ここで言う「他人」とは、演じる役の人物のことです。
なぜ「自分から」なのか?
もしこの出発点をすっ飛ばして「役の生きざまだけ」を生きてしまったら、どうなるでしょうか。
誰がやっても同じになってしまいます。
「この役を演じるのは、あなたである必要がないじゃないか」
そう問われた時、答えられるでしょうか。私たちが本当に見たいのは、その俳優だからこそ生まれる「登場人物の生きざま」なのです。
日本の新劇が教えてくれたこと
この演技のスタイルには、歴史的な背景があります。
第一次世界大戦の頃、ロシアからスタニスラフスキーの「システム演技」が日本に伝わりました。文部科学省から派遣された演出家・小山内薫がロシアで学び、築地小劇場で「会話劇」を始めたのです。これが「新劇」の始まりでした。
小山内氏の弟子である久保栄先生は、こう教えました。
「俳優に大事なことは、自分から始まって他人の顔を被る必要がある。だから自分のことをよく知る必要があるよ」
役の視点と自分の視点を比較し、「どこが共感できて、どこが共感できないのか」を見つけ出す。これが俳優の仕事の第一歩なのです。
「セリフは結果」—プロセスを分解せよ
今回の稽古で最も重要だったのは、この考え方でした。
セリフは「結果」である。その結果に至るまでの「プロセス」をどれだけ意識的に踏めるかが、演技のクオリティを決める。
処理の数が芝居の密度を決める
セリフを出すスピードが早いと、一つひとつのプロセスを処理できません。結果だけを追う芝居になってしまいます。
プロセスには、こんな要素が含まれます。
- 呼吸
- 表情
- 筋肉の緊張
- 目線
- 口の形
- ボディランゲージ
- 音、明るさ、匂い
- 重力、場所の影響
ある俳優への指導では、「処理するプロセスが3、4個増えている」と評価されながらも、「まだ容量が余っている。5、6個突っ込めるんじゃないか」とさらなる可能性が指摘されました。
「聴く」という仕事にもプロセスがある
舞台上で喋っていない俳優の仕事は何でしょうか?
「聴くこと」ですが、それは単に黙って立っているのではありません。**「反応」**が必要です。そしてその反応にも、反応に行き着くまでのプロセスが不可欠なのです。
ボディランゲージ、呼吸、表情、目線—幕が開いてから閉じるまで、全員がこのプロセスを積み続けることが、芝居の**「リアリティ」**につながります。
「リザルト演技」という落とし穴
特に危険なのが、**「結果からイメージを取る」**演技スタイルです。
リザルト演技の構造
- セリフ(結果)を読み、「このセリフは悲しい」「このシーンは辛い」というイメージを先に持つ
- そのイメージから演技を始める
- 相手の表情や芝居(プロセス)を見ても、「悲しいだろうな」という結果の確認にしかならない
- 相手が笑っていても「悲しいけど笑ってるんだな」となり、相手の芝居が自分の結果を裏打っても変わらない
「どんなにプロセスを100個積んでも、結果は一緒」
これでは、何回も稽古した場面を「目の前で初めて起こった出来事かのように」演じるという、俳優の使命を果たせません。結果を知っている人の話になってしまい、それは**「作業」**でしかないのです。
技術論:ビアネガティブとキネスフィア
具体的な技術として、二つのアプローチが紹介されました。
ビアネガティブ—「足す」のではなく「やめる」
**ビアネガティブ(Be Negative)**とは、芝居の要素に何かを足すのではなく、何かをやめることで表現の幅を広げるアプローチです。
稽古では、俳優それぞれの無意識の癖が指摘されました。
- 相手のセリフへの反応時に、瞬きと呼吸ばかり使う癖
→ 別のもの(表情、動き、声、距離感、視線など)で反応を取る - 反応が全て呼吸と表情で、動きがない。ウィスパーボイスの癖
→ 呼吸と表情以外のもので反応を取り、芝居の可能性を広げる - 反応を下を向いて取る癖
→ 下を向くと「ネガティブ」「助からないと分かっている結果」に見えるため、上を向くなど別の方向を試す - 立ち上がる時に後ろに引く癖、重心が前に倒れている癖
→ 前方向に立ち上がる、重心を後ろに置くことで印象を変える
キネスフィアとコントラスト
背が高くエネルギーの強い俳優には、「弱」をどう作るかが課題となります。
キネスフィアとは、身体が空間に占める領域の概念です。「キネスフィアを小さくする。小さく狭く、内向きに持っていく」ことで、芝居にコントラストが生まれ、表現の幅が広がります。
また、声の出し方が身体の全方向に力がかかる「筋肉の緊張」になっている場合、意識的に重心をずらしたり、力を抜いたりする工夫が必要です。
俳優の精神性—「楽しさ」と「自己認識」
技術論と同じくらい大切なのが、俳優の心構えです。
お芝居は「楽しいもの」という大前提
「芝居は厳しくやるもの」という認識がある俳優に、演出家はこう語りました。
「楽しいものっていう大前提がないと、限界が来る」
「楽しい」は「楽」ではありません。楽と楽しいは違うのです。
「音楽やらなかったら死ぬ」といった極端な言葉で表現する姿勢も批判されました。重要なのは、**「好きだから。やりたいから」**という純粋な動機です。
お芝居は「そもそも楽しいんだ」という原点に立ち返ることで、忍耐力と楽しさが融合し、さらに素晴らしい俳優へと成長できるのです。
フィードバックとの向き合い方
キャリアを積んだ俳優が成長を止めてしまう要因の一つが、フィードバックとの向き合い方です。
フィードバックに対して「言われたくない」という表情や態度が出てしまうと、指導する側も「言わない方がいいのかな」と遠慮してしまいます。
「あなたが言われない状況を作っているんだよ」
「私はここはやっている」という「できている」意識にフォーカスしすぎると、相手の言葉を聞かなくなってしまいます。
真に成長するためには、毎回ゼロから考える必要があります。「芝居なんてできない」という謙虚さと探求心を持ち続けることが不可欠なのです。
高密度な芝居への道
この日の稽古は、重要な教訓で締めくくられました。
結果だけを追うのではなく、丁寧にプロセスを踏んでいく練習(スローな芝居)と、それを解放したフリーの芝居を交互に行う「ゆり戻し」が重要である。
フリーで演じた際、「1回目よりクオリティが上がっている」ことは確認されましたが、客観的には「まだ情報の密度が緩い」状態でした。
この繰り返しを行うことで、「お客さんが高速度でも取りこぼさないぐらい」の高密度な芝居へと進化していけるのです。
俳優は常に、無意識の癖を意識化し、繊細なプロセスを積み重ねることで、観客に「初めて起こった出来事かのように」感じさせるリアリティを追求し続けなければなりません。
それは終わりのない旅です。しかし、その旅を楽しむことができれば、俳優として、人として、成長し続けることができるのです。